食事、ADHD、ハイパーフィクセーション | なぜいつも同じものを食べてしまうのか?
いつも同じものを食べてしまう?食事を忘れる?料理が負担? ADHDの食生活をもっとシンプルにするヒントを紹介します。
いつも同じものを食べてしまう?食事を忘れる?料理が負担? ADHDの食生活をもっとシンプルにするヒントを紹介します。
コンテンツ注意: この記事では「食事」「食習慣」「摂食の困難」について言及しています。必要に応じて、地域の支援機関やNEDA(全米摂食障害協会)、CHADDなどの専門団体をご利用ください。
多くのADHDのある人にとって、食事は単なる栄養補給ではありません。感情、感覚、そして安心感とのつながりでもあります。同じものを何週間も食べ続けたり、理由の分からない不規則な食生活に悩んだりすることがあるかもしれません。それは「フード・ハイパーフィクセーション(食への強いこだわり)」と呼ばれることもあります。一見安心感がある一方で、もどかしさも感じやすい状態です。
ハイパーフィクセーション自体が悪いわけではありません。その背景を理解することで、自分をよりやさしくサポートできるようになります。ADHDが食にどのように影響するかを知ることは、自分に合った、柔軟で続けやすい食習慣をつくるための第一歩です。
ハイパーフィクセーションとは、特定の物事に頭が集中してしまい、そこから離れるのが難しくなる状態を指します。食に関しては、同じおやつや食事を何度も繰り返して食べたくなるなど、「慣れていて安心」「取り組みやすい」「満足感がある」などの理由から起こることが多いです。
ハイパーフィクセーションはADHDや自閉スペクトラムのコミュニティでよく語られます。両者に共通点はありますが、「ハイパーフォーカス」とは異なります。ハイパーフォーカスは目的志向で時間を忘れるほど集中する状態。一方ハイパーフィクセーションは、特に食に関しては「止めようとしても止められない」ような衝動性が関わることもあります。
「食生活が極端になりやすい」と感じるなら、ADHDの特性が関係しているかもしれません。以下のような要素が影響します:
食べるのを忘れてしまったり、空腹を感じるまで食事を先延ばしにしたり——これらはADHDでよく見られる傾向です。その結果、エネルギーや感情のバランスが取りにくくなることも。
感情が高ぶったとき、食事が心を落ち着ける手段になることがあります。これは空腹よりも「頭の中の混乱を落ち着かせたい」という欲求が原因の場合もあります。
同じシリアルやサンドイッチにハマった経験はありませんか? こうした「こだわりの食」は、日々の中で予測可能性や安心感を与えてくれるものでもあります。
感覚刺激を求めたり、逆に避けたりするADHDの特性によって、「安心できる食べ物」だけを食べ続けることもあります。ADHDの人たちにとってよくある「セーフフード(安心食)」については、このRedditのスレッドでも紹介されています。
買い物、調理、献立決めなどの一連の流れが「ハードルが高すぎる」と感じることも。そんな時は、実行機能と料理に関するガイド を参考にしてみてください。
原因は人それぞれですが、ADHDと関係するいくつかの要素があります:
ADHDの脳はドーパミンを強く求めます。塩味・甘味・脂っこさなどが際立つ「ハイパーパラタブル(刺激的で快感を得やすい)な食べ物」は、短時間でドーパミンを放出し、強い満足感を得られることがあります。
食べ物の食感・香り・味は、ADHDの脳にとって快適な刺激や安心感をもたらすもの。パリッとしたチップスや、とろけるクリーミーパスタなどがその例です。
「今日は何を食べるか」を毎回考えるのは疲れるもの。決まった食事を繰り返すことで、選択の負荷(decision fatigue)を減らし、日常に安定感をもたらします。
準備、計画、実行に大きな労力が必要なとき、同じ食事を選ぶのは「生き抜くための工夫」でもあります。
この状態は必ずしも悪いものではなく、むしろ困難な時期の「対処手段」として役立つこともあります。ただし、健康に影響が出ていたり、変化を望んでいる場合は、次のような工夫が助けになります:
Tiimoのようなアプリを使えば、食事時間のスケジューリングや買い物リスト、リマインダー設定などが簡単になります。負担が減ることで、実行までのハードルも下がります。
タスクを始められない・継続できない?
Tiimoは、実行機能の困難、タイムアグノジア、フォローアップの難しさに配慮し、視覚的なタイマーやスマートチェックリスト、柔軟なスケジューリングでサポートします。
冷凍野菜やレンジ調理できる穀物、プロテイン入りのスナックなど、「すぐに食べられる安心食材」をストックしておくと、いつもの食事に栄養をプラスできます。
飽きてきたと感じたら、小さな変化から始めましょう。例えば、ピザに新しいトッピングを加える、定番メニューの材料を1つ変えてみる、など。
同じPB&Jサンドを1日3回食べていても、食べているだけでOK!食事を抜かないこと、できたことを評価する姿勢が大切です。
食へのこだわりがつらいと感じたり、摂食障害の傾向がある場合は、ADHDに理解のあるセラピストや管理栄養士のサポートを受けましょう。自閉スペクトラムや感覚過敏との重なりがある場合は特に、専門的な理解が重要です。
フード・ハイパーフィクセーションは、安心材料にもなり、挑戦の種にもなります。ADHDのある人にとって、食へのこだわりは「混乱した日々に安心感をもたらす支え」でもあります。
変化を望むときは、小さな一歩から。新しいトッピングを試したり、気が向いたときにだけ違うメニューにしてみたり。大切なのは「安心して続けられること」です。完璧である必要はありません。自分の脳と体にやさしい選択ができれば、それで十分です。
必ずしもそうではありません。これは「安心したい」「考える負荷を減らしたい」など、自分を整えるための方法でもあります。ただし、つらさやストレスが大きい場合は、専門家への相談をおすすめします。
あります。特に忙しい時期やストレスが多い時期には、同じ食事を繰り返すことで「栄養がとれている」「何も考えずに食べられる」といった安心感が生まれます。
はっきり分けるのは難しいですが、「楽しさやラクさで選んでいるか」「やめたいと思ってもやめられないか」で判断すると良いでしょう。
あります。ADHDではドーパミン欲求や感覚刺激、実行機能が関係し、「味が濃い・手軽・心地よい食べ物」にこだわる傾向が見られます。一方、自閉スペクトラムでは、感覚過敏や予測可能性の確保が大きな要因となり、「食感・香り・温度」が安心の基準になります。
必ずしもそうではありません。困っていないなら無理に変える必要はありません。むしろ「お気に入りの数種類をローテーションする」など、自分に合う柔軟な工夫で十分です。
いつも同じものを食べてしまう?食事を忘れる?料理が負担? ADHDの食生活をもっとシンプルにするヒントを紹介します。
コンテンツ注意: この記事では「食事」「食習慣」「摂食の困難」について言及しています。必要に応じて、地域の支援機関やNEDA(全米摂食障害協会)、CHADDなどの専門団体をご利用ください。
多くのADHDのある人にとって、食事は単なる栄養補給ではありません。感情、感覚、そして安心感とのつながりでもあります。同じものを何週間も食べ続けたり、理由の分からない不規則な食生活に悩んだりすることがあるかもしれません。それは「フード・ハイパーフィクセーション(食への強いこだわり)」と呼ばれることもあります。一見安心感がある一方で、もどかしさも感じやすい状態です。
ハイパーフィクセーション自体が悪いわけではありません。その背景を理解することで、自分をよりやさしくサポートできるようになります。ADHDが食にどのように影響するかを知ることは、自分に合った、柔軟で続けやすい食習慣をつくるための第一歩です。
ハイパーフィクセーションとは、特定の物事に頭が集中してしまい、そこから離れるのが難しくなる状態を指します。食に関しては、同じおやつや食事を何度も繰り返して食べたくなるなど、「慣れていて安心」「取り組みやすい」「満足感がある」などの理由から起こることが多いです。
ハイパーフィクセーションはADHDや自閉スペクトラムのコミュニティでよく語られます。両者に共通点はありますが、「ハイパーフォーカス」とは異なります。ハイパーフォーカスは目的志向で時間を忘れるほど集中する状態。一方ハイパーフィクセーションは、特に食に関しては「止めようとしても止められない」ような衝動性が関わることもあります。
「食生活が極端になりやすい」と感じるなら、ADHDの特性が関係しているかもしれません。以下のような要素が影響します:
食べるのを忘れてしまったり、空腹を感じるまで食事を先延ばしにしたり——これらはADHDでよく見られる傾向です。その結果、エネルギーや感情のバランスが取りにくくなることも。
感情が高ぶったとき、食事が心を落ち着ける手段になることがあります。これは空腹よりも「頭の中の混乱を落ち着かせたい」という欲求が原因の場合もあります。
同じシリアルやサンドイッチにハマった経験はありませんか? こうした「こだわりの食」は、日々の中で予測可能性や安心感を与えてくれるものでもあります。
感覚刺激を求めたり、逆に避けたりするADHDの特性によって、「安心できる食べ物」だけを食べ続けることもあります。ADHDの人たちにとってよくある「セーフフード(安心食)」については、このRedditのスレッドでも紹介されています。
買い物、調理、献立決めなどの一連の流れが「ハードルが高すぎる」と感じることも。そんな時は、実行機能と料理に関するガイド を参考にしてみてください。
原因は人それぞれですが、ADHDと関係するいくつかの要素があります:
ADHDの脳はドーパミンを強く求めます。塩味・甘味・脂っこさなどが際立つ「ハイパーパラタブル(刺激的で快感を得やすい)な食べ物」は、短時間でドーパミンを放出し、強い満足感を得られることがあります。
食べ物の食感・香り・味は、ADHDの脳にとって快適な刺激や安心感をもたらすもの。パリッとしたチップスや、とろけるクリーミーパスタなどがその例です。
「今日は何を食べるか」を毎回考えるのは疲れるもの。決まった食事を繰り返すことで、選択の負荷(decision fatigue)を減らし、日常に安定感をもたらします。
準備、計画、実行に大きな労力が必要なとき、同じ食事を選ぶのは「生き抜くための工夫」でもあります。
この状態は必ずしも悪いものではなく、むしろ困難な時期の「対処手段」として役立つこともあります。ただし、健康に影響が出ていたり、変化を望んでいる場合は、次のような工夫が助けになります:
Tiimoのようなアプリを使えば、食事時間のスケジューリングや買い物リスト、リマインダー設定などが簡単になります。負担が減ることで、実行までのハードルも下がります。
タスクを始められない・継続できない?
Tiimoは、実行機能の困難、タイムアグノジア、フォローアップの難しさに配慮し、視覚的なタイマーやスマートチェックリスト、柔軟なスケジューリングでサポートします。
冷凍野菜やレンジ調理できる穀物、プロテイン入りのスナックなど、「すぐに食べられる安心食材」をストックしておくと、いつもの食事に栄養をプラスできます。
飽きてきたと感じたら、小さな変化から始めましょう。例えば、ピザに新しいトッピングを加える、定番メニューの材料を1つ変えてみる、など。
同じPB&Jサンドを1日3回食べていても、食べているだけでOK!食事を抜かないこと、できたことを評価する姿勢が大切です。
食へのこだわりがつらいと感じたり、摂食障害の傾向がある場合は、ADHDに理解のあるセラピストや管理栄養士のサポートを受けましょう。自閉スペクトラムや感覚過敏との重なりがある場合は特に、専門的な理解が重要です。
フード・ハイパーフィクセーションは、安心材料にもなり、挑戦の種にもなります。ADHDのある人にとって、食へのこだわりは「混乱した日々に安心感をもたらす支え」でもあります。
変化を望むときは、小さな一歩から。新しいトッピングを試したり、気が向いたときにだけ違うメニューにしてみたり。大切なのは「安心して続けられること」です。完璧である必要はありません。自分の脳と体にやさしい選択ができれば、それで十分です。
必ずしもそうではありません。これは「安心したい」「考える負荷を減らしたい」など、自分を整えるための方法でもあります。ただし、つらさやストレスが大きい場合は、専門家への相談をおすすめします。
あります。特に忙しい時期やストレスが多い時期には、同じ食事を繰り返すことで「栄養がとれている」「何も考えずに食べられる」といった安心感が生まれます。
はっきり分けるのは難しいですが、「楽しさやラクさで選んでいるか」「やめたいと思ってもやめられないか」で判断すると良いでしょう。
あります。ADHDではドーパミン欲求や感覚刺激、実行機能が関係し、「味が濃い・手軽・心地よい食べ物」にこだわる傾向が見られます。一方、自閉スペクトラムでは、感覚過敏や予測可能性の確保が大きな要因となり、「食感・香り・温度」が安心の基準になります。
必ずしもそうではありません。困っていないなら無理に変える必要はありません。むしろ「お気に入りの数種類をローテーションする」など、自分に合う柔軟な工夫で十分です。
いつも同じものを食べてしまう?食事を忘れる?料理が負担? ADHDの食生活をもっとシンプルにするヒントを紹介します。
コンテンツ注意: この記事では「食事」「食習慣」「摂食の困難」について言及しています。必要に応じて、地域の支援機関やNEDA(全米摂食障害協会)、CHADDなどの専門団体をご利用ください。
多くのADHDのある人にとって、食事は単なる栄養補給ではありません。感情、感覚、そして安心感とのつながりでもあります。同じものを何週間も食べ続けたり、理由の分からない不規則な食生活に悩んだりすることがあるかもしれません。それは「フード・ハイパーフィクセーション(食への強いこだわり)」と呼ばれることもあります。一見安心感がある一方で、もどかしさも感じやすい状態です。
ハイパーフィクセーション自体が悪いわけではありません。その背景を理解することで、自分をよりやさしくサポートできるようになります。ADHDが食にどのように影響するかを知ることは、自分に合った、柔軟で続けやすい食習慣をつくるための第一歩です。
ハイパーフィクセーションとは、特定の物事に頭が集中してしまい、そこから離れるのが難しくなる状態を指します。食に関しては、同じおやつや食事を何度も繰り返して食べたくなるなど、「慣れていて安心」「取り組みやすい」「満足感がある」などの理由から起こることが多いです。
ハイパーフィクセーションはADHDや自閉スペクトラムのコミュニティでよく語られます。両者に共通点はありますが、「ハイパーフォーカス」とは異なります。ハイパーフォーカスは目的志向で時間を忘れるほど集中する状態。一方ハイパーフィクセーションは、特に食に関しては「止めようとしても止められない」ような衝動性が関わることもあります。
「食生活が極端になりやすい」と感じるなら、ADHDの特性が関係しているかもしれません。以下のような要素が影響します:
食べるのを忘れてしまったり、空腹を感じるまで食事を先延ばしにしたり——これらはADHDでよく見られる傾向です。その結果、エネルギーや感情のバランスが取りにくくなることも。
感情が高ぶったとき、食事が心を落ち着ける手段になることがあります。これは空腹よりも「頭の中の混乱を落ち着かせたい」という欲求が原因の場合もあります。
同じシリアルやサンドイッチにハマった経験はありませんか? こうした「こだわりの食」は、日々の中で予測可能性や安心感を与えてくれるものでもあります。
感覚刺激を求めたり、逆に避けたりするADHDの特性によって、「安心できる食べ物」だけを食べ続けることもあります。ADHDの人たちにとってよくある「セーフフード(安心食)」については、このRedditのスレッドでも紹介されています。
買い物、調理、献立決めなどの一連の流れが「ハードルが高すぎる」と感じることも。そんな時は、実行機能と料理に関するガイド を参考にしてみてください。
原因は人それぞれですが、ADHDと関係するいくつかの要素があります:
ADHDの脳はドーパミンを強く求めます。塩味・甘味・脂っこさなどが際立つ「ハイパーパラタブル(刺激的で快感を得やすい)な食べ物」は、短時間でドーパミンを放出し、強い満足感を得られることがあります。
食べ物の食感・香り・味は、ADHDの脳にとって快適な刺激や安心感をもたらすもの。パリッとしたチップスや、とろけるクリーミーパスタなどがその例です。
「今日は何を食べるか」を毎回考えるのは疲れるもの。決まった食事を繰り返すことで、選択の負荷(decision fatigue)を減らし、日常に安定感をもたらします。
準備、計画、実行に大きな労力が必要なとき、同じ食事を選ぶのは「生き抜くための工夫」でもあります。
この状態は必ずしも悪いものではなく、むしろ困難な時期の「対処手段」として役立つこともあります。ただし、健康に影響が出ていたり、変化を望んでいる場合は、次のような工夫が助けになります:
Tiimoのようなアプリを使えば、食事時間のスケジューリングや買い物リスト、リマインダー設定などが簡単になります。負担が減ることで、実行までのハードルも下がります。
タスクを始められない・継続できない?
Tiimoは、実行機能の困難、タイムアグノジア、フォローアップの難しさに配慮し、視覚的なタイマーやスマートチェックリスト、柔軟なスケジューリングでサポートします。
冷凍野菜やレンジ調理できる穀物、プロテイン入りのスナックなど、「すぐに食べられる安心食材」をストックしておくと、いつもの食事に栄養をプラスできます。
飽きてきたと感じたら、小さな変化から始めましょう。例えば、ピザに新しいトッピングを加える、定番メニューの材料を1つ変えてみる、など。
同じPB&Jサンドを1日3回食べていても、食べているだけでOK!食事を抜かないこと、できたことを評価する姿勢が大切です。
食へのこだわりがつらいと感じたり、摂食障害の傾向がある場合は、ADHDに理解のあるセラピストや管理栄養士のサポートを受けましょう。自閉スペクトラムや感覚過敏との重なりがある場合は特に、専門的な理解が重要です。
フード・ハイパーフィクセーションは、安心材料にもなり、挑戦の種にもなります。ADHDのある人にとって、食へのこだわりは「混乱した日々に安心感をもたらす支え」でもあります。
変化を望むときは、小さな一歩から。新しいトッピングを試したり、気が向いたときにだけ違うメニューにしてみたり。大切なのは「安心して続けられること」です。完璧である必要はありません。自分の脳と体にやさしい選択ができれば、それで十分です。
必ずしもそうではありません。これは「安心したい」「考える負荷を減らしたい」など、自分を整えるための方法でもあります。ただし、つらさやストレスが大きい場合は、専門家への相談をおすすめします。
あります。特に忙しい時期やストレスが多い時期には、同じ食事を繰り返すことで「栄養がとれている」「何も考えずに食べられる」といった安心感が生まれます。
はっきり分けるのは難しいですが、「楽しさやラクさで選んでいるか」「やめたいと思ってもやめられないか」で判断すると良いでしょう。
あります。ADHDではドーパミン欲求や感覚刺激、実行機能が関係し、「味が濃い・手軽・心地よい食べ物」にこだわる傾向が見られます。一方、自閉スペクトラムでは、感覚過敏や予測可能性の確保が大きな要因となり、「食感・香り・温度」が安心の基準になります。
必ずしもそうではありません。困っていないなら無理に変える必要はありません。むしろ「お気に入りの数種類をローテーションする」など、自分に合う柔軟な工夫で十分です。
When you're ready, try Tiimo and make structure a little easier.

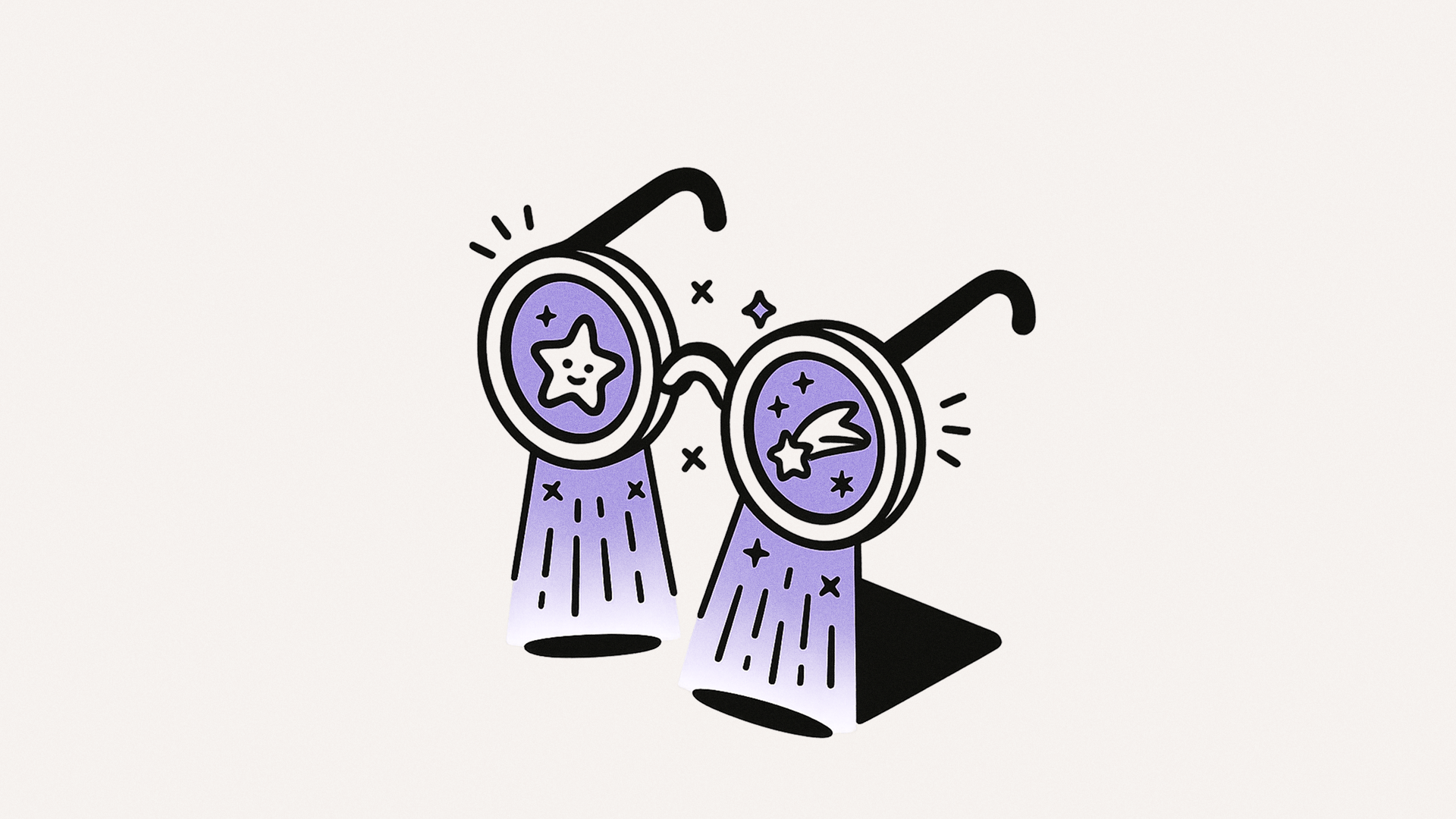
Sometimes you don't have the time or energy to learn new strategies to succeed. That's why we present three simple micro-strategies to help you get things done, when you are feeling overwhelmed and defeated.

Being productive isn’t always about doing more. It’s about managing your energy. This article explains why a short, daily check-in with your brain’s battery matters. Like your phone needs to be charged, your brain needs it too.

Tiimo has been awarded the iPhone App of the Year at the 2025 App Store Awards, an honor given to only a select group of products each year. This post looks back at the learnings that have shaped the last decade of our journey.