AuDHDとは?ADHDと自閉スペクトラムが重なるとき
ADHDと自閉スペクトラムが重なる「AuDHD」。その特徴や暮らしを楽にするヒントを紹介します。
ADHDと自閉スペクトラムが重なる「AuDHD」。その特徴や暮らしを楽にするヒントを紹介します。
長年、自分の脳が自分に逆らっているように感じてきました。構造を必要としているのに抵抗してしまう。深い集中を求めているのに、実行機能に悩まされる。刺激を求めながら、感情には過敏すぎる。そんな矛盾のなかで、ようやく「AuDHD(オーディーエイチディー)」という言葉に出会い、すべてがつながりました。
もしあなたも「頭の中で違うルールが同時に働いている気がする」と感じたことがあるなら、それはあなただけではありません。
AuDHDとは、自閉スペクトラムとADHDという2つの神経タイプが重なり合った状態を指します。よく「片方はルーティンを好み、もう片方は新しさを求める」と対照的に語られがちですが、実際にはもっと複雑です。
AuDHDは単なる「自閉スペクトラム+ADHD」ではなく、2つの特性が相互に影響し合い、ときに矛盾すらする、まったく新しい体験なのです。
それにもかかわらず、多くの専門家はいまだにADHDと自閉スペクトラムを別々の状態として扱っています。2013年以前は、両方を同時に診断することすらできませんでした。
研究では、自閉スペクトラムのある人の20〜50%がADHDの基準も満たし、ADHDのある人の30〜80%に自閉的な傾向が見られるとされています(出典1、出典2)。しかし、診断基準が時代遅れで硬直しているため、多くの人が未診断や誤診のままなのです。
ADHDは多動的、自閉スペクトラムは堅苦しい。そんなイメージがあるかもしれませんが、実際には重なる部分も多く、人によってその現れ方も異なります。
誰ひとりとして、まったく同じADHDや自閉スペクトラムの人はいません。
詳しくは実行機能と神経多様性に関するガイドもご覧ください。

このような内的な矛盾が、AuDHDという体験を独特なものにしており、診断を難しくしている理由でもあります。
多くの人にとって、AuDHDの診断は複雑でアクセスが困難です。DSM-5(精神障害の診断と統計マニュアル)では、自閉スペクトラムとADHDが別々に分類されており、その重なりを十分に考慮していません。この古い枠組みのせいで、多くの人が未診断や誤診のままとなっています(出典3)。
ADHDは衝動的、自閉スペクトラムは硬直的とされますが、両方の特性を併せ持つ人では、これらが互いに目立たなくなることがあります。そのため診断がさらに難しくなります。
特に女性として育てられた人は、症状を隠すためのマスキング(仮面行動)や補償行動を無意識にとっている場合が多く、診断が見逃されがちです。 (詳しくは自閉スペクトラムの女性と女児におけるマスキングをご覧ください)
一部の専門家は、いまだに「自閉スペクトラム=共感性が低い」「ADHD=多動的」といった偏った理解を持っており、より広範な体験が見落とされています。
多くのAuDHDの方は、まず不安障害やうつ病、パーソナリティ障害と誤診されることがあり、本来の診断にたどり着くまでに時間がかかります。
ニューロダイバーシティ(神経多様性)という概念は、ロマ系の活動家で複数の神経タイプを持つKassiane A. Asasumasu氏によって広められました(出典4)。
この視点では、自閉スペクトラムやADHDといった神経の違いを「治すべき障害」ではなく、「人間の自然な認知のバリエーション」と捉えます。つまり、脳の動き方が異なるだけで、それ自体が悪いわけではないのです。
それでも多くのAuDHDの人は、「やりすぎ」「敏感すぎる」「整理できない」「こだわりが強すぎる」と言われ、自分に何か問題があるのではないかと感じてしまいます。
しかし、障害の社会モデルでは、神経多様な人々が直面する困難は、個人の欠陥ではなく「社会の側にある配慮の欠如」によって生まれるとされます。
職場や学校、地域社会が柔軟さやアクセシビリティを重視すれば、AuDHDの特性も障害ではなく「強み」として活かすことができます。
診断があってもなくても、支援は受けて良いのです。待機リストが長かったり、専門家が知識不足だったりしても、自分の脳に合った環境や工夫、コミュニティを持つことはできます。
自閉スペクトラムとADHDの両方を理解し、強みベースの視点で支援してくれるセラピストやコーチ、メンターを探してみましょう。内面化された障害観を手放し、自分に合った戦略を立てる手助けになります。
従来の職場や学校環境は、AuDHDの脳に最適化されていません。感覚面・実行機能・感情面のニーズに合った空間づくりは、日常をぐっと楽にしてくれます。
たとえば:
自分のニーズを言葉にするのは難しいときもありますが、それはとても大切なスキルです。
スクリプト、書面でのリクエスト、直接のやりとりなど、自分が安心できる方法を使って大丈夫です。
たとえば:
「わかってもらえる」ことは本当に大切です。対面でもオンラインでも、神経多様性に配慮したスペースは孤立感を和らげ、共感と安心をくれます。
同じような経験を持つ人が集まるグループやミートアップ、フォーラムを探してみてください。 TiimoのRedditフォーラムも良いスタート地点です。
AuDHDのある人は、しばしば自分の脳に合っていない社会のなかで生きづらさを感じます。でも、それはあなただけの責任ではありません。
この道のりを1人で進む必要はないのです。
まだ知り始めたばかりの方も、長年そう感じてきた方も、あなたには支援と理解を受ける権利があります。
自分に優しくしましょう。あなたを大切にしてくれる人を見つけてください。
そして何より——問題はあなたの脳ではなく、あなたの脳に合っていない「仕組み」のほうかもしれません。だからこそ、自分のやり方で生きやすい毎日をつくっていいのです。
もっと読みたい方はこちら では、ADHDや自閉スペクトラム、神経多様性にやさしい仕事や生活の工夫について紹介しています。
ADHDと自閉スペクトラムが重なる「AuDHD」。その特徴や暮らしを楽にするヒントを紹介します。
長年、自分の脳が自分に逆らっているように感じてきました。構造を必要としているのに抵抗してしまう。深い集中を求めているのに、実行機能に悩まされる。刺激を求めながら、感情には過敏すぎる。そんな矛盾のなかで、ようやく「AuDHD(オーディーエイチディー)」という言葉に出会い、すべてがつながりました。
もしあなたも「頭の中で違うルールが同時に働いている気がする」と感じたことがあるなら、それはあなただけではありません。
AuDHDとは、自閉スペクトラムとADHDという2つの神経タイプが重なり合った状態を指します。よく「片方はルーティンを好み、もう片方は新しさを求める」と対照的に語られがちですが、実際にはもっと複雑です。
AuDHDは単なる「自閉スペクトラム+ADHD」ではなく、2つの特性が相互に影響し合い、ときに矛盾すらする、まったく新しい体験なのです。
それにもかかわらず、多くの専門家はいまだにADHDと自閉スペクトラムを別々の状態として扱っています。2013年以前は、両方を同時に診断することすらできませんでした。
研究では、自閉スペクトラムのある人の20〜50%がADHDの基準も満たし、ADHDのある人の30〜80%に自閉的な傾向が見られるとされています(出典1、出典2)。しかし、診断基準が時代遅れで硬直しているため、多くの人が未診断や誤診のままなのです。
ADHDは多動的、自閉スペクトラムは堅苦しい。そんなイメージがあるかもしれませんが、実際には重なる部分も多く、人によってその現れ方も異なります。
誰ひとりとして、まったく同じADHDや自閉スペクトラムの人はいません。
詳しくは実行機能と神経多様性に関するガイドもご覧ください。

このような内的な矛盾が、AuDHDという体験を独特なものにしており、診断を難しくしている理由でもあります。
多くの人にとって、AuDHDの診断は複雑でアクセスが困難です。DSM-5(精神障害の診断と統計マニュアル)では、自閉スペクトラムとADHDが別々に分類されており、その重なりを十分に考慮していません。この古い枠組みのせいで、多くの人が未診断や誤診のままとなっています(出典3)。
ADHDは衝動的、自閉スペクトラムは硬直的とされますが、両方の特性を併せ持つ人では、これらが互いに目立たなくなることがあります。そのため診断がさらに難しくなります。
特に女性として育てられた人は、症状を隠すためのマスキング(仮面行動)や補償行動を無意識にとっている場合が多く、診断が見逃されがちです。 (詳しくは自閉スペクトラムの女性と女児におけるマスキングをご覧ください)
一部の専門家は、いまだに「自閉スペクトラム=共感性が低い」「ADHD=多動的」といった偏った理解を持っており、より広範な体験が見落とされています。
多くのAuDHDの方は、まず不安障害やうつ病、パーソナリティ障害と誤診されることがあり、本来の診断にたどり着くまでに時間がかかります。
ニューロダイバーシティ(神経多様性)という概念は、ロマ系の活動家で複数の神経タイプを持つKassiane A. Asasumasu氏によって広められました(出典4)。
この視点では、自閉スペクトラムやADHDといった神経の違いを「治すべき障害」ではなく、「人間の自然な認知のバリエーション」と捉えます。つまり、脳の動き方が異なるだけで、それ自体が悪いわけではないのです。
それでも多くのAuDHDの人は、「やりすぎ」「敏感すぎる」「整理できない」「こだわりが強すぎる」と言われ、自分に何か問題があるのではないかと感じてしまいます。
しかし、障害の社会モデルでは、神経多様な人々が直面する困難は、個人の欠陥ではなく「社会の側にある配慮の欠如」によって生まれるとされます。
職場や学校、地域社会が柔軟さやアクセシビリティを重視すれば、AuDHDの特性も障害ではなく「強み」として活かすことができます。
診断があってもなくても、支援は受けて良いのです。待機リストが長かったり、専門家が知識不足だったりしても、自分の脳に合った環境や工夫、コミュニティを持つことはできます。
自閉スペクトラムとADHDの両方を理解し、強みベースの視点で支援してくれるセラピストやコーチ、メンターを探してみましょう。内面化された障害観を手放し、自分に合った戦略を立てる手助けになります。
従来の職場や学校環境は、AuDHDの脳に最適化されていません。感覚面・実行機能・感情面のニーズに合った空間づくりは、日常をぐっと楽にしてくれます。
たとえば:
自分のニーズを言葉にするのは難しいときもありますが、それはとても大切なスキルです。
スクリプト、書面でのリクエスト、直接のやりとりなど、自分が安心できる方法を使って大丈夫です。
たとえば:
「わかってもらえる」ことは本当に大切です。対面でもオンラインでも、神経多様性に配慮したスペースは孤立感を和らげ、共感と安心をくれます。
同じような経験を持つ人が集まるグループやミートアップ、フォーラムを探してみてください。 TiimoのRedditフォーラムも良いスタート地点です。
AuDHDのある人は、しばしば自分の脳に合っていない社会のなかで生きづらさを感じます。でも、それはあなただけの責任ではありません。
この道のりを1人で進む必要はないのです。
まだ知り始めたばかりの方も、長年そう感じてきた方も、あなたには支援と理解を受ける権利があります。
自分に優しくしましょう。あなたを大切にしてくれる人を見つけてください。
そして何より——問題はあなたの脳ではなく、あなたの脳に合っていない「仕組み」のほうかもしれません。だからこそ、自分のやり方で生きやすい毎日をつくっていいのです。
もっと読みたい方はこちら では、ADHDや自閉スペクトラム、神経多様性にやさしい仕事や生活の工夫について紹介しています。
ADHDと自閉スペクトラムが重なる「AuDHD」。その特徴や暮らしを楽にするヒントを紹介します。
長年、自分の脳が自分に逆らっているように感じてきました。構造を必要としているのに抵抗してしまう。深い集中を求めているのに、実行機能に悩まされる。刺激を求めながら、感情には過敏すぎる。そんな矛盾のなかで、ようやく「AuDHD(オーディーエイチディー)」という言葉に出会い、すべてがつながりました。
もしあなたも「頭の中で違うルールが同時に働いている気がする」と感じたことがあるなら、それはあなただけではありません。
AuDHDとは、自閉スペクトラムとADHDという2つの神経タイプが重なり合った状態を指します。よく「片方はルーティンを好み、もう片方は新しさを求める」と対照的に語られがちですが、実際にはもっと複雑です。
AuDHDは単なる「自閉スペクトラム+ADHD」ではなく、2つの特性が相互に影響し合い、ときに矛盾すらする、まったく新しい体験なのです。
それにもかかわらず、多くの専門家はいまだにADHDと自閉スペクトラムを別々の状態として扱っています。2013年以前は、両方を同時に診断することすらできませんでした。
研究では、自閉スペクトラムのある人の20〜50%がADHDの基準も満たし、ADHDのある人の30〜80%に自閉的な傾向が見られるとされています(出典1、出典2)。しかし、診断基準が時代遅れで硬直しているため、多くの人が未診断や誤診のままなのです。
ADHDは多動的、自閉スペクトラムは堅苦しい。そんなイメージがあるかもしれませんが、実際には重なる部分も多く、人によってその現れ方も異なります。
誰ひとりとして、まったく同じADHDや自閉スペクトラムの人はいません。
詳しくは実行機能と神経多様性に関するガイドもご覧ください。

このような内的な矛盾が、AuDHDという体験を独特なものにしており、診断を難しくしている理由でもあります。
多くの人にとって、AuDHDの診断は複雑でアクセスが困難です。DSM-5(精神障害の診断と統計マニュアル)では、自閉スペクトラムとADHDが別々に分類されており、その重なりを十分に考慮していません。この古い枠組みのせいで、多くの人が未診断や誤診のままとなっています(出典3)。
ADHDは衝動的、自閉スペクトラムは硬直的とされますが、両方の特性を併せ持つ人では、これらが互いに目立たなくなることがあります。そのため診断がさらに難しくなります。
特に女性として育てられた人は、症状を隠すためのマスキング(仮面行動)や補償行動を無意識にとっている場合が多く、診断が見逃されがちです。 (詳しくは自閉スペクトラムの女性と女児におけるマスキングをご覧ください)
一部の専門家は、いまだに「自閉スペクトラム=共感性が低い」「ADHD=多動的」といった偏った理解を持っており、より広範な体験が見落とされています。
多くのAuDHDの方は、まず不安障害やうつ病、パーソナリティ障害と誤診されることがあり、本来の診断にたどり着くまでに時間がかかります。
ニューロダイバーシティ(神経多様性)という概念は、ロマ系の活動家で複数の神経タイプを持つKassiane A. Asasumasu氏によって広められました(出典4)。
この視点では、自閉スペクトラムやADHDといった神経の違いを「治すべき障害」ではなく、「人間の自然な認知のバリエーション」と捉えます。つまり、脳の動き方が異なるだけで、それ自体が悪いわけではないのです。
それでも多くのAuDHDの人は、「やりすぎ」「敏感すぎる」「整理できない」「こだわりが強すぎる」と言われ、自分に何か問題があるのではないかと感じてしまいます。
しかし、障害の社会モデルでは、神経多様な人々が直面する困難は、個人の欠陥ではなく「社会の側にある配慮の欠如」によって生まれるとされます。
職場や学校、地域社会が柔軟さやアクセシビリティを重視すれば、AuDHDの特性も障害ではなく「強み」として活かすことができます。
診断があってもなくても、支援は受けて良いのです。待機リストが長かったり、専門家が知識不足だったりしても、自分の脳に合った環境や工夫、コミュニティを持つことはできます。
自閉スペクトラムとADHDの両方を理解し、強みベースの視点で支援してくれるセラピストやコーチ、メンターを探してみましょう。内面化された障害観を手放し、自分に合った戦略を立てる手助けになります。
従来の職場や学校環境は、AuDHDの脳に最適化されていません。感覚面・実行機能・感情面のニーズに合った空間づくりは、日常をぐっと楽にしてくれます。
たとえば:
自分のニーズを言葉にするのは難しいときもありますが、それはとても大切なスキルです。
スクリプト、書面でのリクエスト、直接のやりとりなど、自分が安心できる方法を使って大丈夫です。
たとえば:
「わかってもらえる」ことは本当に大切です。対面でもオンラインでも、神経多様性に配慮したスペースは孤立感を和らげ、共感と安心をくれます。
同じような経験を持つ人が集まるグループやミートアップ、フォーラムを探してみてください。 TiimoのRedditフォーラムも良いスタート地点です。
AuDHDのある人は、しばしば自分の脳に合っていない社会のなかで生きづらさを感じます。でも、それはあなただけの責任ではありません。
この道のりを1人で進む必要はないのです。
まだ知り始めたばかりの方も、長年そう感じてきた方も、あなたには支援と理解を受ける権利があります。
自分に優しくしましょう。あなたを大切にしてくれる人を見つけてください。
そして何より——問題はあなたの脳ではなく、あなたの脳に合っていない「仕組み」のほうかもしれません。だからこそ、自分のやり方で生きやすい毎日をつくっていいのです。
もっと読みたい方はこちら では、ADHDや自閉スペクトラム、神経多様性にやさしい仕事や生活の工夫について紹介しています。
When you're ready, try Tiimo and make structure a little easier.

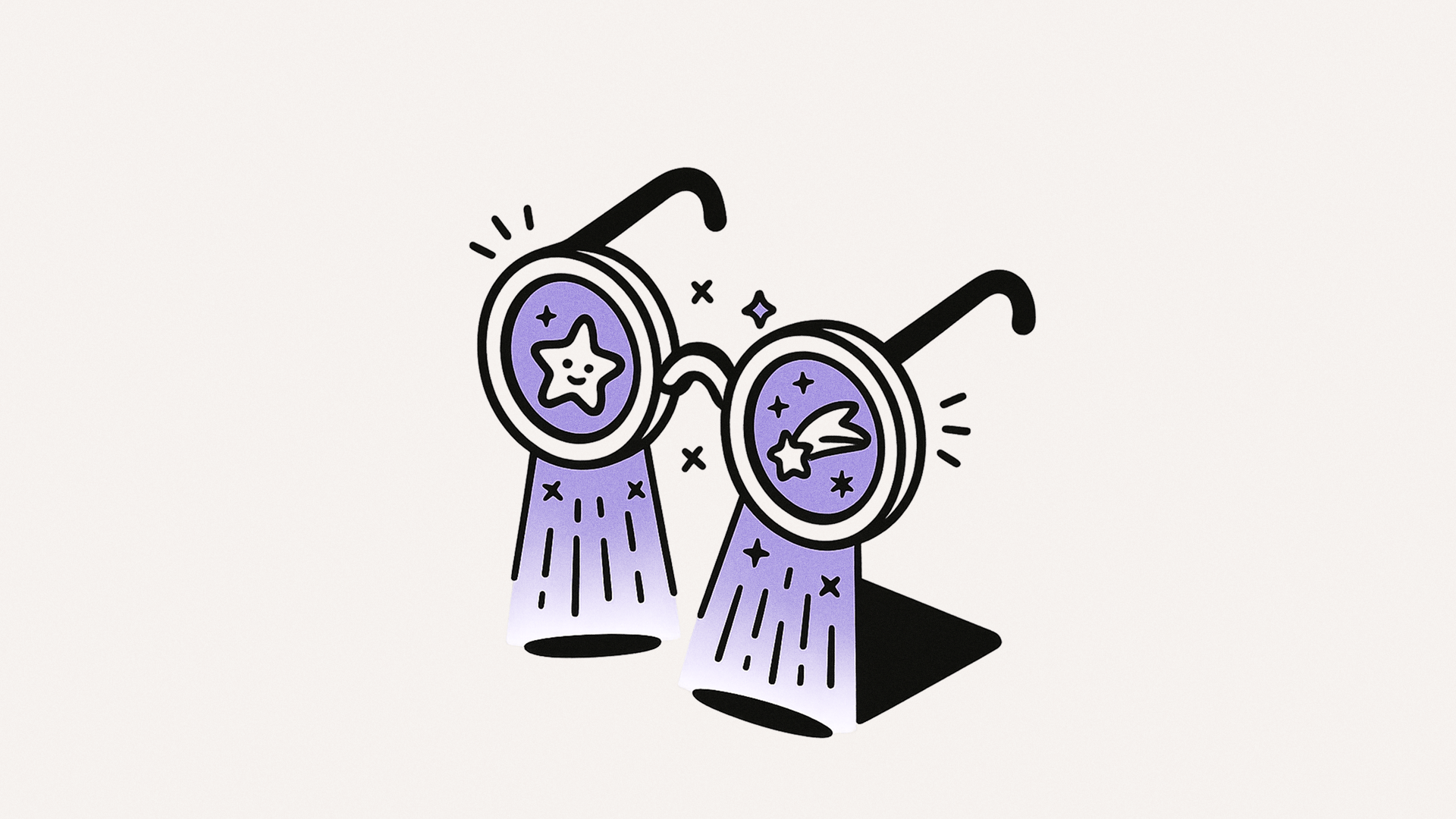
Sometimes you don't have the time or energy to learn new strategies to succeed. That's why we present three simple micro-strategies to help you get things done, when you are feeling overwhelmed and defeated.

Being productive isn’t always about doing more. It’s about managing your energy. This article explains why a short, daily check-in with your brain’s battery matters. Like your phone needs to be charged, your brain needs it too.

Tiimo has been awarded the iPhone App of the Year at the 2025 App Store Awards, an honor given to only a select group of products each year. This post looks back at the learnings that have shaped the last decade of our journey.